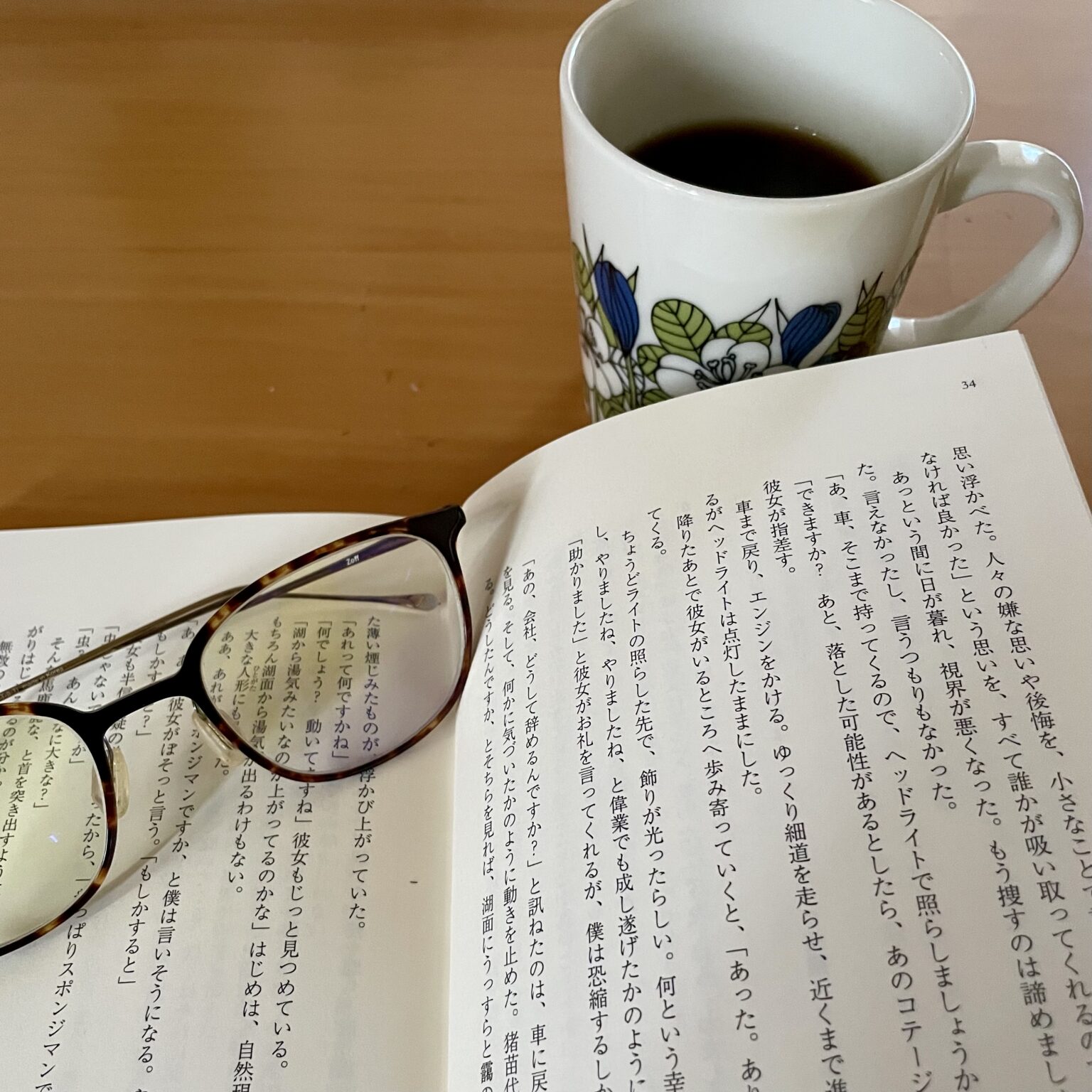お久しぶりの角田光代さん。
『方舟を燃やす』 角田 光代
物語の展開
口さけ女はいなかった。恐怖の大王は来なかった。噂はぜんぶデマだった。一方で大災害が町を破壊し、疫病が流行し、今も戦争が起き続けている。何でもいいから何かを信じないと、何が起きるかわからない今日をやり過ごすことが出来ないよ――。飛馬と不三子、縁もゆかりもなかった二人の昭和平成コロナ禍を描き、「信じる」ことの意味を問いかける傑作長篇。
Amazon内容紹介 より
1967年生まれの飛馬と、戦後すぐに生まれた不三子、2人のそれぞれの暮らしぶりや心情が交互に描かれていく。
飛馬が小学生の頃母が入院し、その病院の談話室で聞いた他の患者同士の話を母のことだと思い込み、母の前で泣いてしまう。
その後母は自殺する。
飛馬は自分のせいで母が悲観したのだという思いを誰にも言えずに背負い続けている。
不三子は、妊娠中に通っていた教会で知り合った人に料理教室に誘われ、食生活の大切さを教わりマクロビオティックに心酔していく。
子供たちには添加物や着色料の入った食べ物は一切食べさせず、給食も拒否、おやつも全部自分で手作りした。
そうして必死で育てたのに、娘は大学を卒業すると家を出て行き音信不通、息子は結婚したけど滅多に連絡はなく孫にも会わせてもらえない。
そんな2人がふとしたきっかけで「こども食堂」で出会う。
飛馬は区役所の職員でこども食堂の運営に関わっている。
不三子は、病院に行った時にたまたま覗いたこども食堂でボランティアスタッフとして参加することになる。

読み終えて
2人それぞれの物語が交互に年代順に書かれていて、全く接点のない彼らがいったいどこでどう繋がるのだろう、つながるんだよね、と思いながら読んだ。
わたしも子育てをしてきたので、やはりどちらかというと不三子に興味持って読んでたけど。

洗脳されてるんちゃう?
それは子どもたちに愛想尽かされてもしかたないよね
そういえば昔そんな人いたの思い出したわ…
なんて思いながら。
でも、本質はそこではない。
こども食堂でベジタリアン料理の試作を食べてもらって「おいしい」と言われた時、「だれにも褒められなかったことを、なぜ四十年も続けられたのか」と自分に驚き、涙が止まらない不三子。
そうなんだ、この人はひたすら家族の健康のことを考え、手を尽くして作った料理を誰にも美味しいと言ってもらえなかったのだ。
夫には食べてもらえず、別の料理を作っていた。
それを40年間続けてきたのだ。
自分が信じたことを続けてきたのだ。
それを考えるとすごいことだなと、ちょっと感動したのだった。
物語全体を通して「何を信じるか」を問われている。

不三子の母親は教師だった。
彼女は「戦争中、言われるままに自分の生徒に挺身隊に入ることを勧め、自分のあたまで考えたことでもないのに、それがただしいと信じて生徒たちを送り込んだ」と語る。
昔も今も「何を信じるのか」。
だまされまいとするあまり、べつのものにだまされているということはないか。(p.388)
吹き込まれたんじゃない、きちんと聞いて、この人の言うことは本当だと自分で判断して、従うと決めたのだ。(p.391)
ただしいはずの真実が、覆ることもあれば、消えることも、にせものだと暴露されることもある。(p.392)
しかたがなかったじゃないか、何がただしいかなんて、みんな知らなかったんだから。(p.408)
神様を信じて乗り込んだ舟だって、この現実では燃え落ちるかもわからないのだ。(p.413)
こういう言葉が怒涛のように押し寄せてくる。
なんだか深く考えさせられた。
もちろん答えは出ない。
ただ、最後の飛馬のターンが「信じる信じない」から「救えるか救えないか、そもそも救いを求めていたのか」みたいなことになってて、ちょっとずれたように感じてしまった。
飛馬が長年背負っていた荷物をおろせたようだし、不三子も自分の人生を生きようと決めたようなので、「よし」ということで。
♫〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
今日も最後までお付き合いくださってありがとうございます ^_^
どうかステキな1日を!